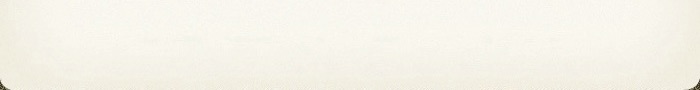2014年収穫ワイン
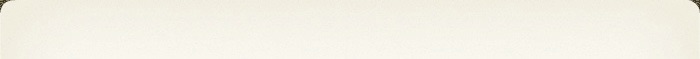


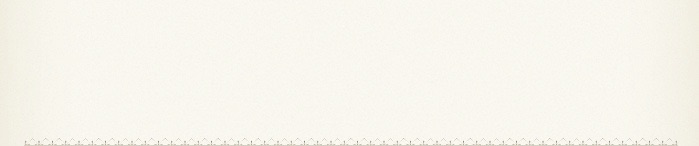


2014年収穫 ミュラー・トゥルガウ醸造報告
2014年は、新生・松原農園にとっては記念すべき最初の年です。ただ、よくあるワイナリーの設立と違うのは、それまでに20年近くも自前のブランドを維持してきたという事です。
この年の第1目標は、「再現」です。北海道ワインでの依託醸造時代の、松原農園ワインのよき特徴を、まずは「小さな、新しい工場で再現できるか」の挑戦であると考えました。
新工場には、今までの依託先のような「スキンコンタクト」(破砕した葡萄を、一定時間浸漬する)する事のできる設備がありません。また、数時間でその年の葡萄をすべて搾っていたのと違い、新工場の小さな搾汁機では、20回以上のサイクルで、「ぶどうの投入」「搾汁」「かす出し」「洗浄」をくり返さなければなりません。

結果的に、一日一日、能率も上がり、最初は日をまたぐくらい遅くまでかかっていた作業も、「数時間の残業」レベルまで能率を上げることが出来ました。また、とても大事な「搾汁率」(どれだけたくさん果汁を搾り取れるか)もジリジリ上がり、満足のいくレベルまでたどり着きました。
私はいつも思うのですが、1回1回の結果の数字ではなく、小さくてもいいから、這うように進み続けること、が何より大事だと思っています。シーズンを通しての数字は平凡でも、翌年に向けての収穫の大きさを感じることが出来ました。

まず、下の写真は一般的な、「除梗破砕」したあとのぶどうの搾汁直前のものです。「果汁の中に、顆粒が浸されている」ような風景です。梗(軸)は外されているため、効率的にたくさんの葡萄を一度に搾ることが出来ます。

これに対して、「ホール・パンチ」では、極めて単純に、「房をそのまま、絞り器に投入する」のです。そしてそのまま搾ってゆきます。どちらかと言えば、かなり「原始的な絞り方」と言えるでしょう。下の写真がその様子です。どう見ても、「葡萄が機械に入れてあるだけ」です。このままハッチを閉じて、圧力をかけて搾ってゆきます。 。。。。。。。。

この絞り方の場合、葡萄の皮が破れていない状態から搾ってゆくため、最初は少しずつしか果汁は得られません。そのため「8割方しぼる」のにかかる時間は何倍も長くかかります。しかし、その真価を発揮するのは、ぶどうの絞りで最も難しい、「あと数%」の段階です。慣行の絞りの場合、これにとても時間がかかる上、「キレイな果汁」は得られず、濁って、「いかにもまずそうな」果汁となってしまいます。しかし、ワイン造りとは「葡萄を液体に変える」事からスタートする以上、「あと少し」でもおろそかにすると大きな損失となります。そのため、悪いのを承知でしぼり続けるか、最後の果汁だけ、「安いワイン」に廻すか、まだ絞れるのを承知で中止するか、対応を迫られます。
ところが、当初はスピードが遅かったホール・パンチ法では、最終盤では大してペースが落ちずに、しかも「キレイな果汁」が出続けます。一緒に投入している梗がフィルターとなり、機械的に破壊されていない効果も合わさって、「時間をかければかけるほど」キレイな果汁が出続けるのです。既存の絞り方の苦労を知っていた私にはこれは本当に驚きでした。結果的に、全体の7割ほどはホール・パンチ法で搾ったのですが、来年度はもう一工夫して、この方法を発展させていきたいと思っています。
もう一つ、新工場らしい設備に助けられた事があります。この新しいステンレスタンクです。

この設備は、春先に瓶詰作業を待っているとき、ワインが醗酵してしまわないように(一度仕上がった甘みの残ったワインが、もう一度発行し始めることを「再発酵」と言って、悩みの種でした)、低温に保つためにも使いました。
(まだまだ続くと思いますが、今日はここら辺で終わりますね。続いては具体的な、松原農園ワインを仕上げるための工夫を解説したいです。)