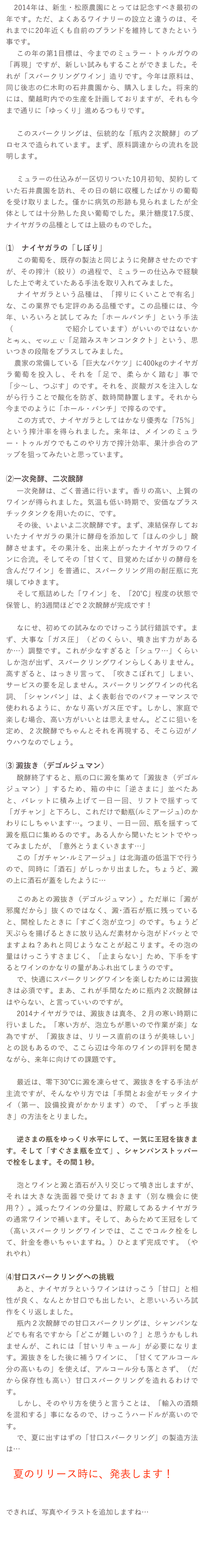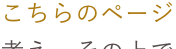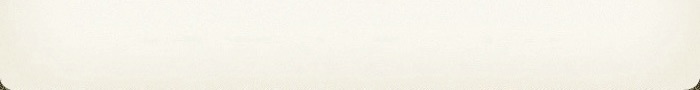2014年収穫ワイン
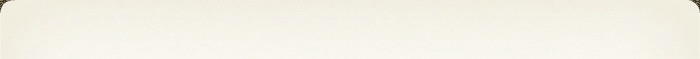





2014年収穫 ナイヤガラスパークリング醸造報告
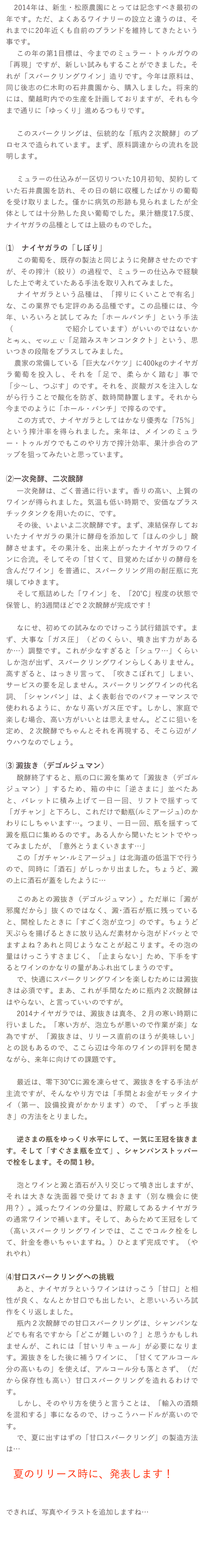
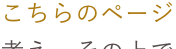

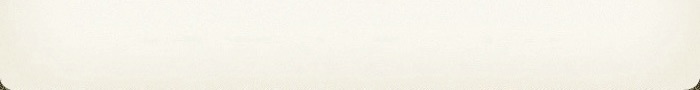
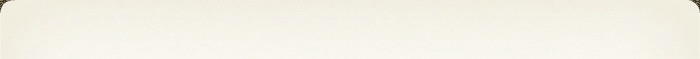

2014年収穫ワイン




2014年収穫 ナイヤガラスパークリング醸造報告